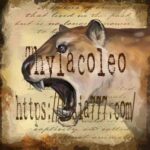マチカネワニのイラストです。
大阪で発見された巨大な新種のワニ。

マチカネワニの特徴
名前/和名:マチカネワニ/待兼鰐
学名:Toyotamaphimeia machikanensis
分類:マチカネワニ属
生息地:日本
大きさ:全長7~8m
食性:魚や小型の水棲動物から、鹿など大型の哺乳類。
特徴:口は鼻先に向けて細長い。頭部から体にかけて全体的に平たい体。
現在のワニと同様に、前足の指は5本、後ろ足の指は4本。
またワニの仲間には珍しく「温帯性」と言われている。
1964年、大阪府豊中市柴原の待兼山丘陵の大阪大学豊中キャンパスにて化石発見。
マレーガビアルの近縁と考えられており、細長く伸びた頭蓋骨などに似ている特徴がある。
※今回のイラストも、マレーガビアルをベースに描かせていただきました。
マチカネワニの名前の由来
マチカネワニの「マチカネ」は出土した場所に由来しますが、
学名は日本の女神様が由来となっております。
学名の流れとしては、
1964年、大阪府豊中市柴原の待兼山丘陵にある、大阪大学豊中キャンパスにて発見。
1965年、トミストマ、マチカネンシスと命名される。
その後1982年、ワニ研究者の青木良輔氏により新種と判明。
1983年、Toyotamaphimeia machikanensis/トヨタマフィメイア・マチカネンシス、と改名。
という流れがあります。
トヨタマフィメイア、という学名は、
日本神話に登場する女神トヨタマヒメが元になっています。
トヨタマヒメは古事記にて、子供を産むときにワニに姿を変えたという伝承があることがその由来になりました。
※今回のイラストはブログにアップするにあたり、当時のイラストに少し加筆、修正を加えています。
※記事の内容はwikiなどを参考に制作いたしました。